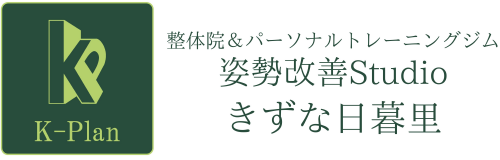「プラセボ効果」という言葉はよく耳にしますが、その反対に、「ノセボ効果」という現象があるのをご存じでしょうか?
ノセボ効果とは、悪い期待や不安によって、痛みや症状が悪化してしまう現象のことです。
この記事では、ノセボ効果の仕組みと、慢性痛にどのように影響しているのかをわかりやすく解説します。
ノセボ効果とは?
ノセボ効果は、簡単に言うと「悪い思い込みが体に影響する現象」です。
たとえば、
- 「この薬は副作用が強い」と言われたあとに実際に不調を感じた
- 「痛みはどんどん悪化するかもしれない」と不安になったら痛みが強まった
といった経験がこれにあたります。
また、もっと身近な例として、
子どものころに嫌いな先生の授業前になると、お腹が痛くなった経験も、ノセボ効果の一例です。
授業への「嫌だな」「怒られるかも」という不安が脳に影響し、実際にお腹の痛みや違和感として体に現れてしまったのです。
なぜノセボ効果で痛みが悪化するのか?
脳は、「危険だ」「痛いはずだ」という期待や予測に非常に敏感です。
こうした不安や恐怖が強くなると、
脳内ではストレスホルモン(コルチゾール)が増え、交感神経が活性化します。
その結果、筋肉の緊張、血流の悪化、神経の過敏化が進み、
実際に痛みが強くなったり、違和感が拡大してしまうのです。
つまり、ノセボ効果は「単なる気のせい」ではなく、
脳と体が本当に生理的に反応して起こる現象だといえます。
ノセボ効果の身近な例:コロナと後遺症不安
最近では、コロナウイルス感染後の後遺症に対する不安も、
ノセボ効果に影響している可能性が指摘されています。
たとえば、
- 「味覚障害がまた出るかも」
- 「体調が悪化するかも」
といった不安を強く持つと、
軽症でも違和感や疲労感を強く感じたり、症状が長引いたりすることがあります。
これは「気のせい」ではなく、
脳の不安反応が身体の感覚を変えてしまうノセボ効果の一種と考えられています。
慢性痛とノセボ効果の関係
慢性痛を抱えている人も、
- 「また痛くなるかも」
- 「このまま悪化するかも」
という不安を抱きやすくなります。
この不安がノセボ効果を引き起こし、痛みの悪循環に陥るケースが少なくありません。
慢性痛とうまく向き合うためには、必要以上に不安を強めないことがとても重要です。
ノセボ効果を防ぐためにできること
- 「痛みがある=悪化している」と短絡的に考えない
- 小さな改善やポジティブな変化に意識を向ける
- ネガティブな情報(必要以上に怖い話)は意識的に距離を取る
- 「よくなる可能性がある」という希望を持つ
痛みがゼロにならなくても、
少しでも楽になった、できることが増えたという小さな変化に気づき、
前向きな感覚を育てていくことが、ノセボ効果を弱めるカギになります。
つまり、プラセボ効果をつくりましょう。
▶プラセボ効果とは?慢性痛や体調改善に与える驚きの力を解説!
まとめ
ノセボ効果は、「脳の予測」が身体に本当の影響を与える現象です。
不安や恐怖にとらわれすぎず、
小さな改善やポジティブな変化に目を向けながら、
少しずつ痛みとの付き合い方を変えていきましょう。
体や心の声に耳を傾けながら、無理なく前向きな選択を積み重ねていくことが大切です。
脳のことや慢性痛についてこちらでまとめています。
▶痛みを和らげる方法まとめ体・心・脳からできるセルフケア